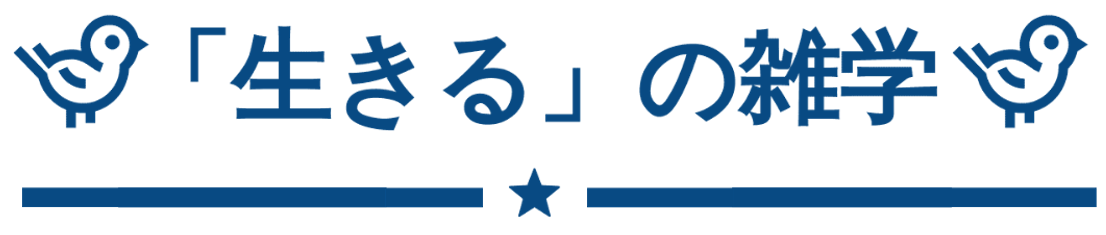生物基礎の「全範囲」の4択問題演習です。
テスト対策や入試対策にご活用ください
400問 演習モード
この分野の問題のすべてを演習できます。
100問 演習モード
50問 演習モード
25問 演習モード
時間がないときにおすすめです。
中間テストや期末テストの対策にご活用ください。
この分野の重要語句一覧
種 共通性 多様性 フック レーウェンフック シュライデン シュワン 細胞説 ウイルス 分解能 顕微鏡 光学顕微鏡 電子顕微鏡 適応 系統 系統樹 代謝 エネルギー 同化 異化 独立栄養生物 従属栄養生物 ATP アデノシン三リン酸 高エネルギーリン酸結合 ADP 炭酸同化 光合成 呼吸 触媒 酵素 基質 基質特異性 最適温度 細胞 原核細胞 真核細胞 原核生物 真核生物 細胞小器官 大腸菌 イシクラゲ 酵母 ミドリムシ 核 核膜 染色体 DNA 酢酸カーミン 酢酸オルセイン 細胞膜 流動モザイクモデル ミトコンドリア 葉緑体 クロロフィル 液胞 細胞液 細胞質基質 原形質流動 細胞壁 セルロース 形質 遺伝子 DNA 染色体 タンパク質 デオキシリボ核酸 ヌクレオチド 糖 塩基 リン酸 デオキシリボース アデニン チミン グアニン シトシン A T G C 塩基対 塩基の相補性 二重らせん構造 水素結合 塩基配列 グリフィス S型菌 R型菌 形質転換 エイブリー ハーシー チェイス ファージ 大腸菌 シャルガフ ワトソン クリック 母細胞 娘細胞 体細胞分裂 鋳型 半保存的複製 分裂期 M期 間期 細胞周期 G1期 S期 G2期 G0期 前期 中期 後期 終期 赤道面 細胞質分裂 酢酸カーミン溶液 アミノ酸 ペプチド結合 一次構造 二次構造 三次構造 四次構造 αヘリックス βシート アミノ基 カルボキシ基 RNA リボ核酸 リボース ウラシル U mRNA tRNA 転写 翻訳 コドン アンチコドン 遺伝子の発現 センタラルドグマ ニーレンバーグ コラーナ 突然変異 多型 一塩基多型 エキソン イントロン スプライシング rRNA ゲノム 生殖細胞 相同染色体 ゲノムプロジェクト 分化 だ腺染色体 パフ iPS細胞 体液 体内環境 外部環境 恒常性 ホメオスタシス 血液 組織液 リンパ液 毛細血管 血糖 グルコース インスリン グルカゴン アドレナリン 糖質コルチコイド 血糖濃度の調節 糖尿病 1型糖尿病 2型糖尿病 自己免疫疾患 ランゲルハンス島B細胞 グリコーゲン 体温の調節 チロキシン 代謝の促進 ふるえ 発汗 血球 血しょう 赤血球 白血球 血小板 血液凝固 フィブリン 線溶 血ぺい 血清 エコノミークラス症候群 トロンビン プロトロンビン フィブリノーゲン 神経細胞 ニューロン 神経系 中枢神経系 体性神経系 自律神経系 末梢神経系 脳 脊髄 感覚神経 運動神経 交感神経 副交感神経 大脳 間脳 中脳 延髄 大脳 小脳 脳幹 視床下部 脳死 植物状態 拮抗的 アセチルコリン ノルアドレナリン シナプス 神経伝達物質 内分泌系 ホルモン 内分泌腺 受容体 標的細胞 標的器官 外分泌腺 排出管 神経分泌細胞 神経分泌 フィードバック 視床下部 放出ホルモン 放出抑制ホルモン 脳下垂体前葉 脳下垂体後葉 成長ホルモン 甲状腺刺激ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン バソプレシン チロキシン パラトルモン すい臓のランゲルハンス島A細胞 B細胞 グルカゴン インスリン 副腎髄質 副腎皮質 アドレナリン 鉱質コルチコイド 糖質コルチコイド 病原体 感染症 角質層 繊毛 粘液 粘膜 デシフェンシン リゾチーム 白血球 食作用 免疫 生体防御 自然免疫 獲得免疫 マクロファージ 好中球 樹状細胞 リンパ球 T細胞 B細胞 ナチュラルキラー細胞 NK細胞 ヘルパーT細胞 キラーT細胞 骨髄 胸腺 扁桃 リンパ節 適応免疫 炎症 抗原 抗原提示 抗体 免疫グロブリン 抗体産生細胞 形質細胞 抗原抗体複合体 抗原抗体反応 免疫寛容 記憶細胞 免疫記憶 二次応答 拒絶反応 自己免疫疾患 関節リウマチ 重症筋無力症 1型糖尿病 アレルギー アレルゲン アナフィラキシーショック IgE 花粉症 マスト細胞 ヒスタミン 免疫不全症 エイズ HIV 日和見感染症 ワクチン 予防接種 血清療法 北里柴三郎 ベーリング 抗体医薬 本庄佑 モノクローナル抗体 植生 優占種 相観 荒原 草原 森林 生活形 土壌 林冠 林床 階層構造 高木層 亜高木層 低木層 草本層 地表層 光合成速度 呼吸速度 見かけの光合成速度 光補償点 光飽和点 陽生植物 陰生植物 陽樹 陰樹 陽葉 陰葉 遷移 先駆種 パイオニア種 共生 極相 クライマックス 極相林 裸地 ギャップ 一次遷移 二次遷移 乾性遷移 湿性遷移 バイオーム 生物群系 年降水量 年平均気温 ツンドラ 針葉樹林 夏緑樹林 照葉樹林 亜熱帯多雨林 熱帯多雨林 雨緑樹林 硬葉樹林 サバンナ ステップ 砂漠 水平分布 マングローブ 常緑広葉樹 落葉広葉樹 常緑針葉樹 垂直分布 森林限界 高山草原 暖かさの指数 チーク クチクラ層 ブナ ミズナラ オリーブ ユーカリ ゲッケイジュ アカシア サボテン トウダイグサ 生態系 非生物的環境 生物的環境 作用 環境形成作用 生産者 消費者 生物多様性 補償深度 食物連鎖 栄養段階 一次消費者 食物網 腐食連鎖 キーストーン種 絶滅 間接効果 撹乱 自然浄化 生態系の復元力 レジリエンス 富栄養化 アオコ 赤潮 温室効果 温室効果ガス 二酸化炭素 メタン フロン サンゴの白化現象 外来生物 侵略的外来生物 オオクチバス フイリマングース 外来生物法 特定外来生物 アマミノクロウサギ 里山 開発 環境アセスメント 絶滅危惧種 レッドリスト レッドデータブック 種の保存法 ワシントン条約 アホウドリ 生態系サービス 持続可能な開発目標 SDGs 生物濃縮 など
参考文献
【理科編 理数編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説
(https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kyoiku02-100002620_06.pdf)
高等学校の生物教育における重要語句の選定について(改訂)
(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190708.pdf)