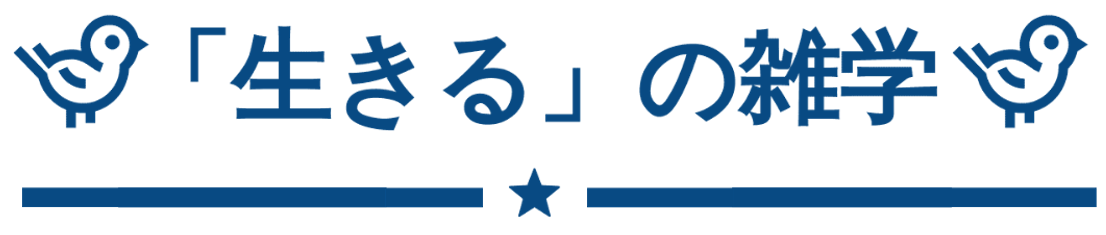生物基礎の「生物の特徴」の分野の4択問題演習です。
テスト対策や入試対策にご活用ください
小単元ごとに学習したい場合はこちらから学習できます。
②細胞
70問 演習モード
この分野の問題のすべてを演習できます。
50問 演習モード
25問 演習モード
10問 演習モード
時間がないときにおすすめです。
中間テストや期末テストの対策にご活用ください。
この分野の重要語句一覧
種 共通性 多様性 フック レーウェンフック シュライデン シュワン 細胞説 ウイルス 分解能 顕微鏡 光学顕微鏡 電子顕微鏡 適応 系統 系統樹 代謝 エネルギー 同化 異化 独立栄養生物 従属栄養生物 ATP アデノシン三リン酸 高エネルギーリン酸結合 ADP 炭酸同化 光合成 呼吸 触媒 酵素 基質 基質特異性 最適温度 細胞 原核細胞 真核細胞 原核生物 真核生物 細胞小器官 大腸菌 イシクラゲ 酵母 ミドリムシ 核 核膜 染色体 DNA 酢酸カーミン 酢酸オルセイン 細胞膜 流動モザイクモデル ミトコンドリア 葉緑体 クロロフィル 液胞 細胞液 細胞質基質 原形質流動 細胞壁 セルロース など
参考文献
【理科編 理数編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説
(https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kyoiku02-100002620_06.pdf)
高等学校の生物教育における重要語句の選定について(改訂)
(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190708.pdf)